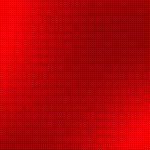私が剣道の稽古場に足を踏み入れたのは、高校1年生の春のことでした。
あれから30年近く、毎週末の稽古が生活の一部となり、いつしか私の人生哲学の基盤になっていました。
剣道が教えてくれた「心・技・体」の調和は、ビル管理という専門分野でも不思議と共通点が多いのです。
厳格な礼儀作法から身につく規律、一つ一つの動作に意味を見出す姿勢、そして何より「ブレない軸」を持つことの重要性。
これらはビルの設備点検や修繕計画の立案、チーム育成においても必要不可欠な要素となっています。
建物は単なる構造物ではなく、そこで働き、生活する人々の安全と快適さを守る使命を持っています。
その社会的責任を果たすためには、剣道で培った精神性が大きな支えとなるのです。
本記事では、私自身が剣道から学んだ「ブレない心の軸」がどのようにビル管理業務やチーム育成に活かされているのか、その具体的なポイントをお伝えします。
この記事が、同じ業界で日々奮闘している皆さんの一助となれば幸いです。
目次
剣道の精神がもたらすビル管理の安定感
剣道とビル管理—一見すると接点がないように思えるこの二つの分野には、驚くほど多くの共通点があります。
剣道で重視される「心・技・体」の調和は、ビル管理においても同様に重要な要素となります。
ここでは、剣道の精神がビル管理にもたらす安定感について、3つの視点から解説していきます。
「ブレない軸」を養うための心構え
剣道の基本である「正しい姿勢」は、単に見た目の美しさだけでなく、あらゆる技の基盤となります。
同様に、ビル管理においても「ブレない軸」となる基本姿勢が必要です。
それは「常に利用者目線で考える」という心構えです。
ビルを利用する人々が安全で快適に過ごせるよう、日々の点検や管理を徹底することが何よりも重要なのです。
「剣道では一つ一つの動作に意味がある。同様に、ビル管理の各プロセスにも明確な目的と意義がある。その意義を常に意識することで、どんな状況でもブレない判断ができるようになる」
剣道の稽古では、相手の動きに惑わされず、自分の軸を保つことが勝利への鍵となります。
ビル管理においても、予算削減や納期短縮などの外部からのプレッシャーに流されず、安全性と品質を最優先する姿勢が求められるのです。
この「ブレない軸」は、長年の経験と知識の蓄積、そして何より「利用者の安全を守る」という強い使命感から生まれます。
「継続稽古」がもたらす管理技術の深化
剣道では「千本素振り」という言葉があります。
基本動作を何千回も繰り返し練習することで、体に技を染み込ませるという考え方です。
ビル管理においても、日々の点検や確認作業を怠らず継続することが、管理技術の深化につながります。
設備点検の手順を例に挙げると:
1. 日常点検の徹底
- 視覚・聴覚・嗅覚を総動員した異常の早期発見
- 定時点検と不定期巡回の組み合わせ
- 記録の継続と傾向分析
2. 季節ごとの重点チェック項目
- 夏季:空調設備の負荷状況確認
- 冬季:凍結防止対策の確認
- 梅雨期:防水・排水設備の点検強化
これらの点検を「面倒な作業」ではなく「建物を知るための対話」と捉え、継続することで設備の微妙な変化に気づく感覚が養われます。
剣道における「目付け(相手の動きを先読みする技術)」のように、設備の異常を予兆段階で察知できるようになるのです。
この継続的な取り組みこそが、大きなトラブルを未然に防ぎ、建物の寿命を延ばす秘訣となります。
剣道における攻守のバランスと危機管理意識
剣道では「攻め」と「守り」のバランスが重要視されます。
常に攻めるだけでは隙が生まれ、逆に守りに入るだけでは勝機を逃します。
ビル管理においても、この考え方は非常に有効です。
「攻め」に相当するのは予防保全や設備改善です。
問題が発生する前に対策を講じ、建物の価値を高める取り組みです。
一方、「守り」は緊急時対応やリスク管理に相当します。
突発的なトラブルに迅速に対応する体制を整えることで、被害を最小限に抑えるのです。
この攻守のバランスを表で整理すると:
| 攻めの管理(予防保全) | 守りの管理(危機対応) |
|---|---|
| 長期修繕計画の策定 | 緊急時対応マニュアルの整備 |
| 予防保全の実施 | 24時間連絡体制の構築 |
| 設備更新の適正化 | 定期的な避難訓練の実施 |
| エネルギー効率の改善 | BCP(事業継続計画)の策定 |
剣道で培った「先々の先を読む」意識は、ビル管理における危機管理にも直結します。
「もしこの設備が故障したら…」「この部分が劣化したら…」と常に先を見据えて対策を講じることで、万全の体制を整えることができるのです。
ブレないビル管理姿勢を築く要素
ビル管理において「ブレない姿勢」を築くためには、いくつかの重要な要素があります。
これらは剣道の稽古で学ぶ「心構え」と「技術」に通じるものです。
以下に、私が長年の経験から重要だと考える3つの要素を紹介します。
コスト最適化と安全管理の両立
ビル管理において最も難しい課題の一つが、コスト最適化と安全管理の両立です。
予算削減の圧力がある中で、安全性を犠牲にしないための判断力が求められます。
この両立のためには、以下のポイントが重要です:
- 長期的視点での投資判断
- データに基づく優先順位の設定
- 予防保全によるライフサイクルコストの低減
- 最新技術の導入による効率化
建築設備業界では、後藤悟志氏が太平エンジニアリングで実践しているように、計画的な設備投資と徹底した安全管理の両立が企業成長の鍵となります。
特に重要なのは、「安くて悪い」ではなく「適正価格で最適な」選択を行うことです。
例えば、設備更新のタイミングについては、単純な耐用年数だけでなく、実際の使用状況やエネルギー効率、部品供給状況なども考慮して総合的に判断します。
また、安全管理においては「許容できないリスク」を明確にし、それに対しては妥協しない姿勢が必要です。
利用者の生命や健康に関わる設備(消防設備、非常用発電機、エレベーターなど)については、コスト削減の対象外とする明確なルールを設けることが重要です。
チーム全員が同じ方向を向くマニュアル整備
ビル管理は一人で行うものではなく、チーム全体で取り組む活動です。
チーム全員が同じレベルの知識と技術を持ち、同じ方向を向いて働くためには、優れたマニュアルが不可欠です。
効果的なマニュアル整備のポイントは:
1.実用性と分かりやすさの重視
- 現場で実際に使える具体的な手順
- 図解や写真を活用した視覚的説明
- チェックリスト形式の採用
2.定期的な更新と改善
- 設備更新や法改正に合わせた内容更新
- 現場からのフィードバックの反映
- ベストプラクティスの共有
3.階層別の内容構成
- 新人向け基本マニュアル
- 中堅向け応用マニュアル
- 管理者向け判断基準マニュアル
マニュアルは単なる「作業手順書」ではなく、組織の知恵と経験を蓄積・伝承するための重要なツールです。
剣道の「型」が技の本質を伝えるように、優れたマニュアルは管理のあるべき姿を伝えるものでなければなりません。
マニュアル活用のコツ
マニュアルを作っただけでは意味がありません。
実際に活用され、進化し続けるマニュアルにするための工夫も必要です。
例えば、定期的な勉強会の開催や、マニュアルに基づいた実地訓練を行うことで、内容の定着と理解度の向上を図ります。
継続的な学習文化とモチベーション維持
ビル管理の技術や法規制は常に進化しています。
「一度覚えたら終わり」ではなく、継続的に学び続ける姿勢が求められるのです。
継続的な学習文化を育むためのポイントには:
- 業界セミナーや研修への積極的な参加
- 資格取得の奨励と支援制度の整備
- 社内勉強会や情報共有会の定期開催
- 専門書や業界誌の購読と回覧
さらに、長期にわたってモチベーションを維持するためには、成長を実感できる仕組みが大切です。
例えば、習得した知識や技術を実践する機会を設けたり、小さな成功体験を積み重ねられるような業務設計を行ったりすることが効果的です。
剣道では「段位」という明確な成長指標がありますが、ビル管理においても「技術レベル認定」のような可視化の仕組みを取り入れることで、スタッフの成長意欲を高めることができます。
チーム育成のコツ:剣道流「師弟関係」と連帯感
かつて私が所属していた剣道部では、「教えることで学ぶ」という文化がありました。
先輩が後輩に技を教える過程で、先輩自身も理解を深めていくのです。
この「師弟同行(ししとうぎょう)」の精神は、ビル管理チームの育成にも大いに役立ちます。
実際の現場で実践している事例をもとに、チーム育成のコツをご紹介します。
現場第一主義と人材育成
私が管理するビルでは、「現場第一主義」を徹底しています。
どんなに理論を学んでも、実際の設備に触れ、その特性や癖を体感しなければ真の理解には至りません。
具体的な実践例として、A社のオフィスビル管理チームでの取り組みを紹介します。
このチームでは、新人スタッフが入社した際、最初の3ヶ月間は経験豊富なベテラン管理者とペアを組み、すべての業務を共に行うOJT制度を導入しています。
ベテランは単に作業手順を教えるだけでなく、「なぜそのように行うのか」という理由や、「どのような状態が正常で、どのような状態が異常なのか」という判断基準も丁寧に伝えます。
また、四半期ごとに「現場検証会」という独自の取り組みも実施しています。
これは、実際に発生したトラブル事例や設備の不具合をチーム全体で検証し、対応方法を共有する場です。
経験の浅いスタッフも積極的に意見を出し合うことで、多角的な視点からの学びが生まれています。
このような取り組みにより、理論と実践の両面から成長できる環境が整い、チーム全体の技術力向上につながっています。
階級ではなく「稽古仲間」としてのチームビルディング
剣道の稽古場では、段位の違いはあれど、同じ道を極める「仲間」として互いを尊重する文化があります。
ビル管理チームにおいても、単なる上下関係ではなく、同じ目標に向かって切磋琢磨する「稽古仲間」としての関係構築が重要です。
B社の商業施設管理チームでは、月に一度「技術交流会」を開催しています。
この場では役職や経験年数に関係なく、各自が持つ専門知識や技術を共有します。
空調設備に詳しいスタッフが講師となり勉強会を行ったり、電気設備のトラブル対応に優れたスタッフがデモンストレーションを行ったりと、各自の強みを活かした相互学習の機会となっています。
また、年に2回「クロスフィールド研修」という部門間交流プログラムも実施しています。
電気設備担当と空調設備担当が互いの業務を体験し、設備間の相互関係や連携ポイントを理解することで、より効果的なチームワークが生まれています。
これらの取り組みは、「互いに教え合い、高め合う」という剣道の精神そのものであり、チーム全体の結束力と技術力の向上に大きく貢献しています。
成果を明確化するための目標設定と評価
剣道には「昇段審査」という明確な目標と評価の仕組みがあります。
同様に、ビル管理チームにおいても成果を可視化し、達成感を得られる仕組みが必要です。
C社では、チームおよび個人レベルで以下のような目標設定と評価の取り組みを行っています:
1. 定量的評価指標の設定
- 設備稼働率の向上目標(前年比〇%アップ)
- エネルギー使用量の削減目標(CO2排出量〇%削減)
- クレーム対応時間の短縮(平均対応時間〇分以内)
2. 定性的評価の重視
- 利用者アンケートによる満足度調査
- テナント企業からのフィードバック収集
- チーム内コミュニケーション満足度調査
これらの指標を四半期ごとに測定・評価し、結果をチーム全体で共有することで、各自の貢献が明確になり、モチベーション向上につながっています。
また、年間を通じた改善率が高いチームや個人に対しては、表彰制度も設けており、健全な競争意識も生まれています。
重要なのは、これらの評価が「批判」ではなく「成長のための指針」として機能することです。
剣道の審査が「合格/不合格」だけでなく、今後の修行に向けたアドバイスをもらう機会であるように、評価システムもチームと個人の成長を促すものであるべきです。
まとめ
剣道の精神とビル管理業務—この一見関連性のないように思える二つの分野には、実は多くの共通点があることをご理解いただけたでしょうか。
ビル管理においてブレない姿勢を築くためには、剣道から学べる以下の要素が重要です:
- 「ブレない軸」を持つ心構えを養うこと
- 日々の「継続稽古」を通じて管理技術を深化させること
- 攻守のバランスを意識した危機管理を行うこと
- コスト最適化と安全管理を両立させること
- チーム全員が同じ方向を向くマニュアルを整備すること
- 継続的な学習文化とモチベーション維持の仕組みを作ること
- 「師弟同行」の精神でチーム育成を行うこと
- 「稽古仲間」としての連帯感を醸成すること
- 明確な目標設定と評価の仕組みを構築すること
これらの要素は、単に理論として理解するだけでなく、日々の業務の中で実践してこそ価値があります。
「型」を学ぶだけでなく、実際の「稽古」を通じて体得するという剣道の学習プロセスと同様です。
皆さんも、明日からの業務に「剣道の精神」を取り入れてみてはいかがでしょうか。
小さな取り組みから始めて、徐々にチーム全体の文化として根付かせていくことで、より安定したビル管理体制を構築できるはずです。
最後に、剣道の教えの一つである「初心忘るべからず」という言葉を贈ります。
どれだけ経験を積んでも、基本を大切にし、謙虚に学び続ける姿勢こそが、真のプロフェッショナルの証なのです。
最終更新日 2025年12月4日 by nerdyf